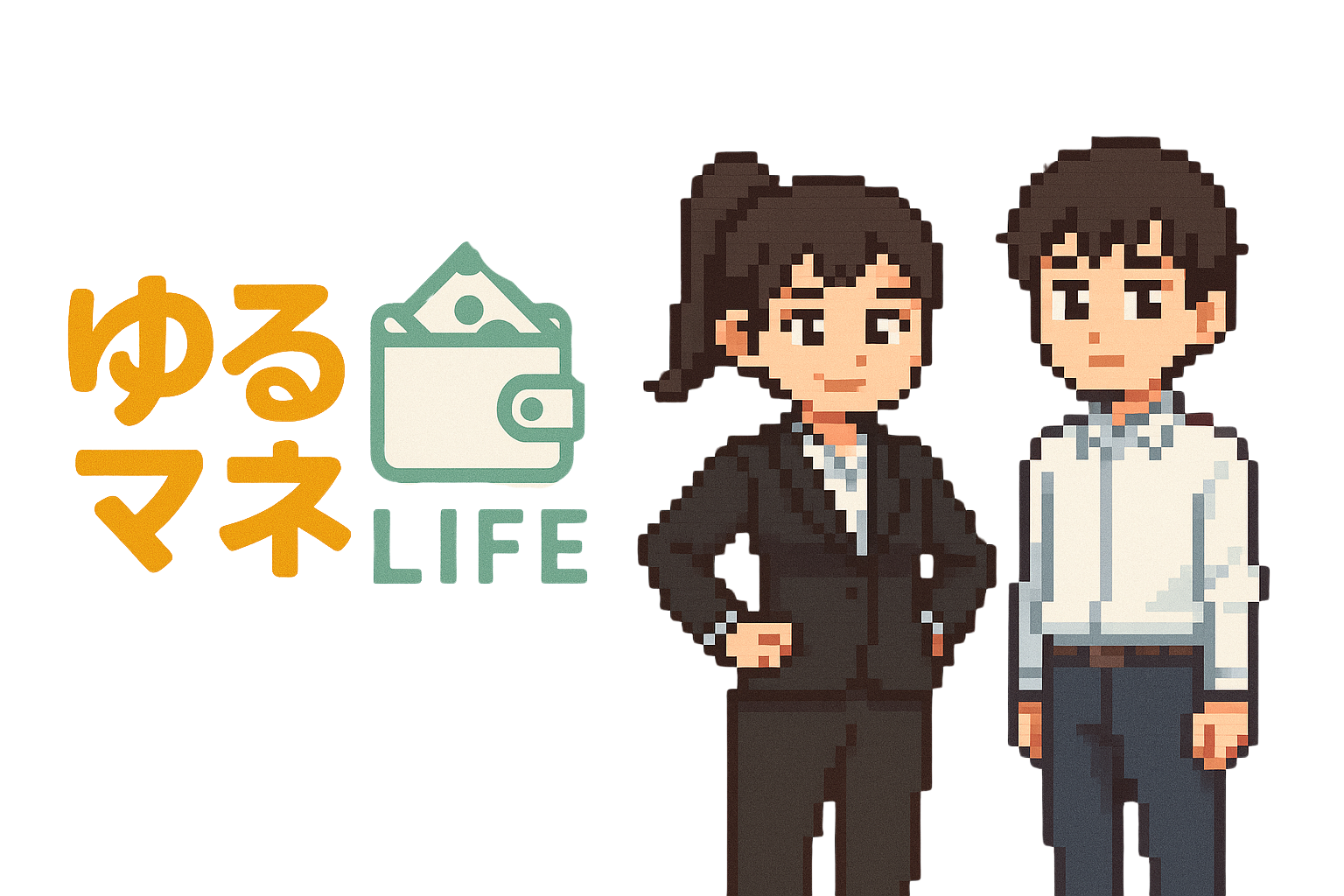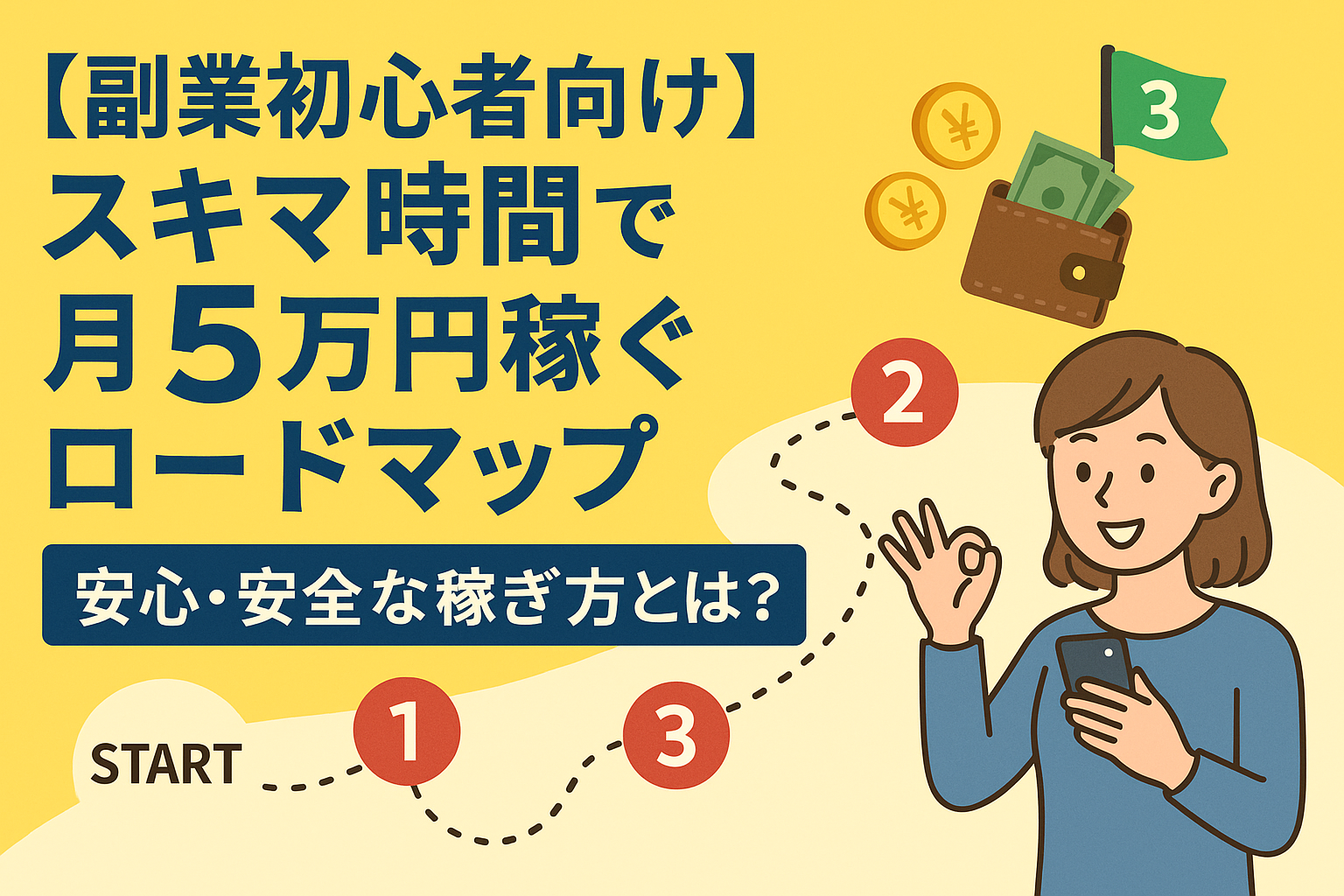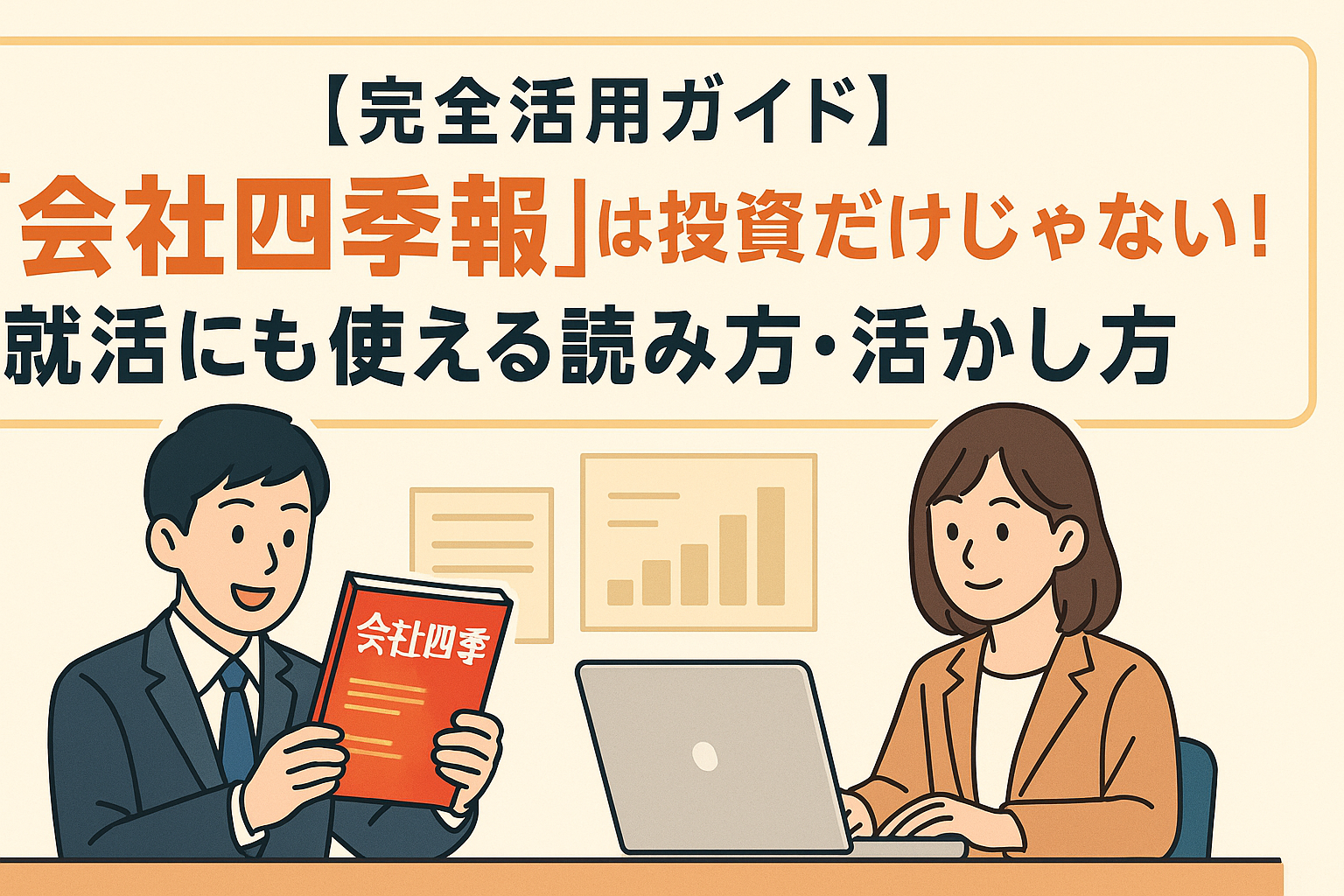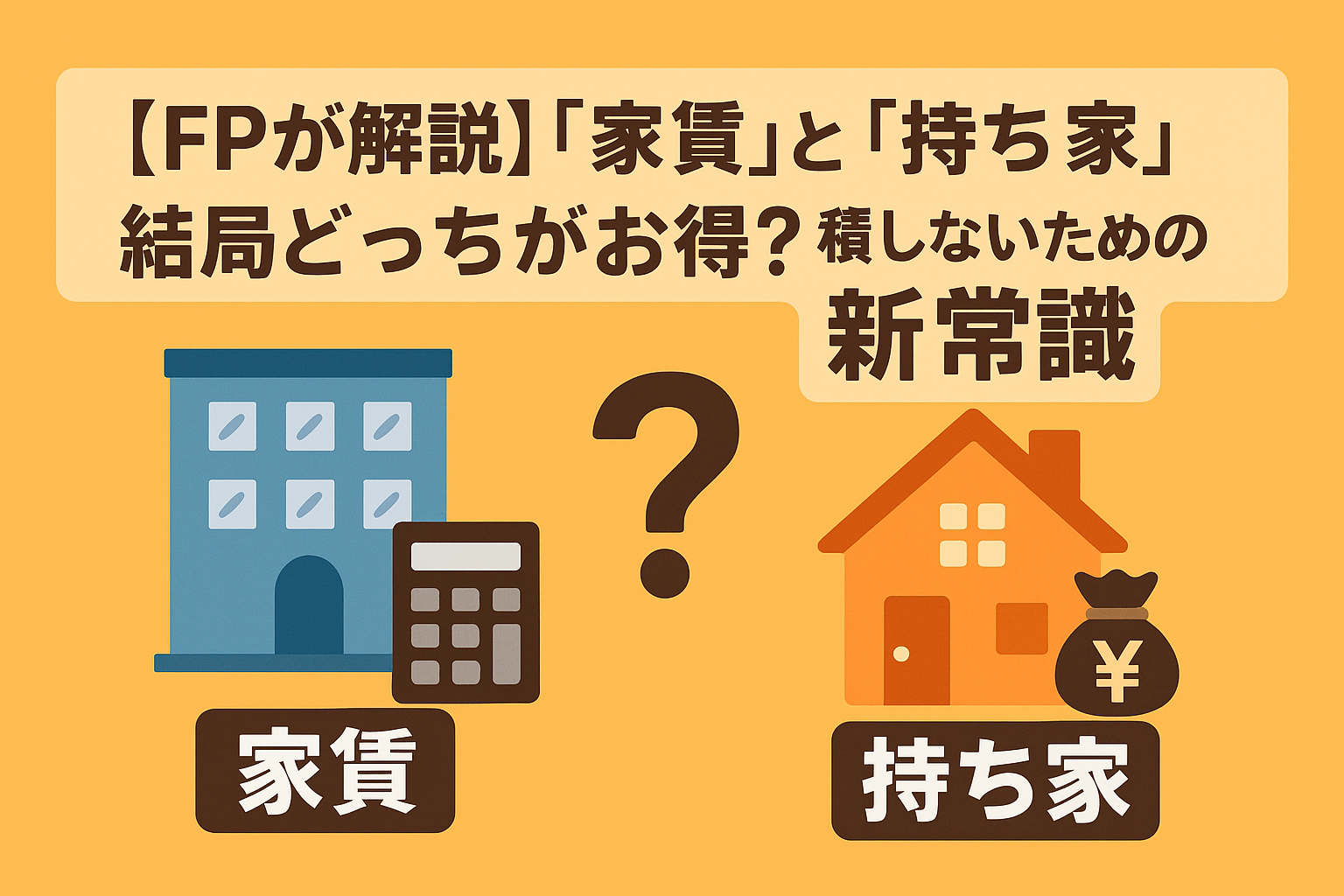【20代の落とし穴】「お金の相談、誰にする?」信頼できない情報源の見分け方
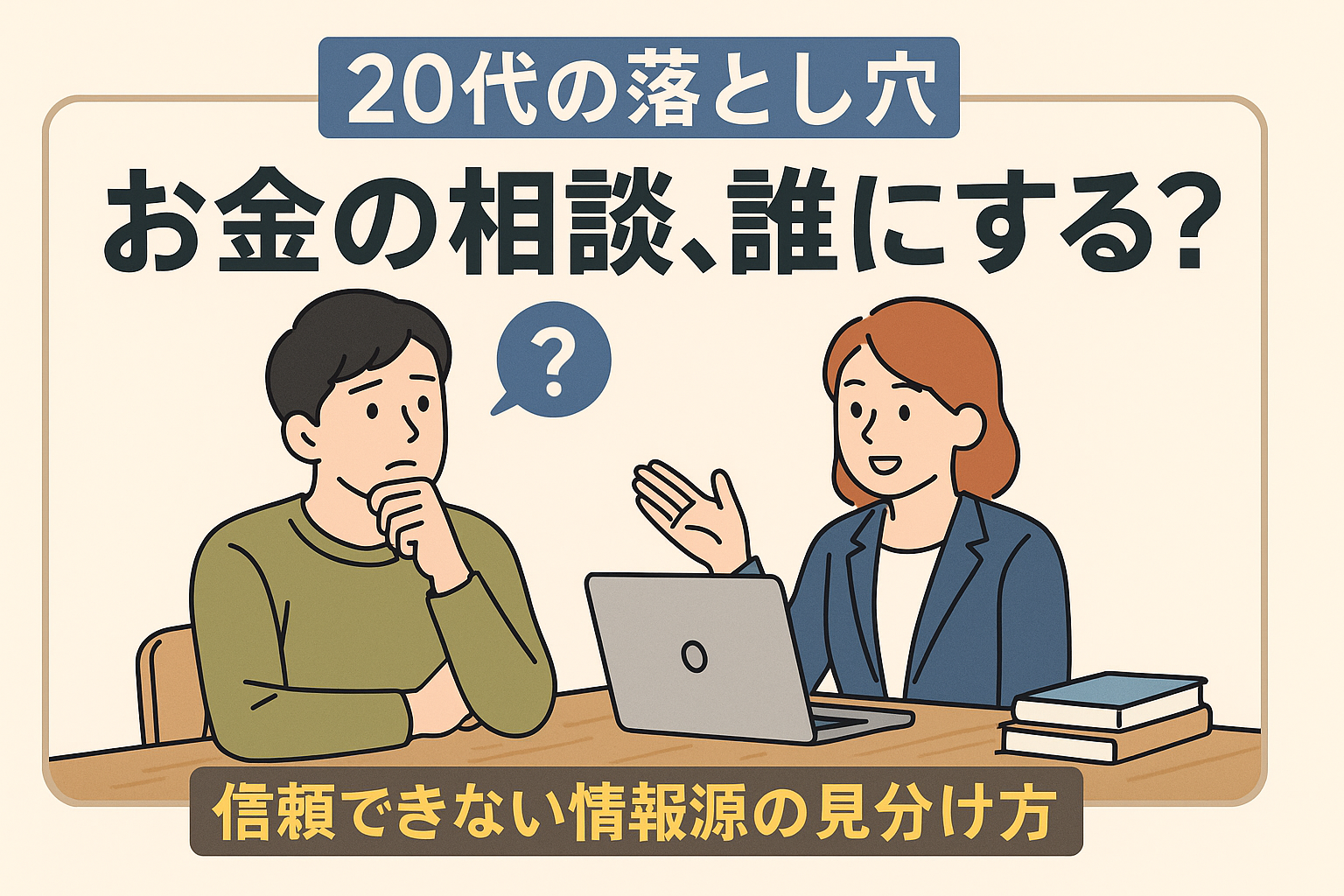
「スマホ1台で月100万円!」その甘い言葉、本当に信じて大丈夫?
SNSを開けば、「スマホ一つで簡単に稼げる」「元本保証で高利回り」といった、魅力的なお金儲けの話が溢れていますよね。
「将来のために何か始めなきゃ…」 「でも、何が本当の情報で、何が嘘の情報か分からない…」
そう思っている人は多いのではないでしょうか?お金に関する情報は、人生を豊かにする力を持つ一方で、一歩間違えれば、あなたの貴重な貯金や信用を失うリスクにもつながります。特に、情報を見極める経験が少ない20代は、その甘い誘惑に陥りやすい世代です。
この記事では、
- なぜ若者が「お金儲け」の話に騙されやすいのか
- 信頼できる情報源と、そうでない情報源をどう見分けるか
- 困ったときに頼れる「お金の相談相手」の見つけ方
を徹底的に解説します。お金に関する情報を自分で判断する力を身につけ、「怪しい話」から自分を守るための知識を身につけましょう。
なぜ若者が「お金儲け」の話に騙されやすいのか?
なぜ、若者は甘い言葉に惹かれてしまうのでしょうか?その背景には、いくつかの理由があります。
- 将来への漠然とした不安:
- 収入や貯金が少なく、将来の生活や老後に対して漠然とした不安を抱えているため、「一発逆転」を狙いがちです。
- 情報過多による判断力の低下:
- SNSやインターネット上には膨大な情報が溢れており、何が正しい情報かを冷静に判断するのが難しくなっています。
- 「みんなやっているから大丈夫」という心理:
- SNSでキラキラした生活を発信しているインフルエンサーを見て、「みんな成功しているから、自分もやれば成功できる」と思い込んでしまうことがあります。
- 高額な情報商材やセミナーへの勧誘:
- 「無料で教えます」と謳いながら、最終的に高額な情報商材やセミナーの購入を勧めてくる手口に引っかかってしまうことがあります。
「信頼できる情報源」と「そうでない情報源」を見分ける3つのチェックポイント
お金に関する情報を見極めるために、以下の3つのポイントを意識して情報をチェックする習慣をつけましょう。
1. 発信者の信頼性をチェックする
誰がその情報を発信しているのか、その人物に信頼性はあるでしょうか?
- 専門資格の有無: ファイナンシャルプランナー(FP)、税理士、弁護士など、専門的な資格を持っているか確認しましょう。資格は、一定の知識と倫理観があることの証明になります。
- 実績と経歴: 具体的な実績や経歴が明確に示されているでしょうか?「〇〇の資格を持っています」「過去に〇〇の会社で働いていました」など、裏付けのある情報があるか確認しましょう。
- 顔出しや実名での発信: もちろん、匿名でも信頼できる発信者はいますが、顔出しや実名で発信している人の方が、より責任を持って情報を発信していると判断できることが多いです。
2. 内容の客観性をチェックする
その情報は、感情的な煽りではなく、客観的な事実に基づいているでしょうか?
- 甘い誘い文句に要注意: 「絶対に儲かる」「元本保証」「誰でも簡単に」といった言葉は、投資の世界ではあり得ません。これらの言葉を使っている時点で、その情報の信頼性は低いと判断しましょう。
- 具体的なデータや根拠の有無: 「みんなやってます」ではなく、「〇〇のデータによると…」「〇〇の制度を利用すると…」など、具体的な根拠やデータが示されているか確認しましょう。
- メリットだけでなく、デメリットやリスクも提示されているか: 信頼できる情報源は、メリットだけでなく、デメリットやリスクも公平に伝えてくれます。良い話ばかりしている情報には注意が必要です。
3. 手数料の透明性をチェックする
その情報に、何らかの商品の購入やサービスの利用が伴う場合、手数料は明確にされていますか?
- 手数料が明確か: 投資信託や保険など、何らかの商品を勧める際、手数料が明確にされているか確認しましょう。「無料」と謳っていても、実は見えない手数料がかかっていることもあります。
- 高額な初期費用に要注意: 「まずは〇〇円の教材を買ってください」「〇〇万円のセミナーに参加してください」といった、高額な初期費用を要求してくる話は、詐欺の可能性が高いです。
困ったときに頼れる「お金の相談相手」の見つけ方
お金のことで悩んだとき、一人で抱え込まず、誰かに相談することはとても大切です。
1. 専門家
お金のプロに相談することで、あなたに合った最適なアドバイスがもらえます。
- ファイナンシャルプランナー(FP): 家計の収支見直し、貯蓄、投資、保険、老後資金など、お金に関する幅広い相談に乗ってくれます。
- 税理士: 確定申告や節税対策など、税金に関する専門的な相談ができます。
2. 公的機関
- 消費生活センター: 詐欺や悪質商法など、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。消費者ホットライン**「188(いやや!泣き寝入り)」**に電話すると、最寄りの相談窓口につながります。
- 税務署: 税金に関する相談に乗ってくれます。確定申告の時期には、相談窓口が設けられます。
3. 友人・知人
身近な友人や知人に相談するのも良いですが、そのアドバイスはあくまで参考程度にとどめ、鵜呑みにしないようにしましょう。友人・知人には、お金に関する専門的な知識があるとは限らないからです。最終的には、自分で調べて判断する習慣を身につけることが重要です。
まとめ:お金に関する情報は「自分で調べて、自分で判断」が鉄則!
お金に関する情報は、あなたの人生を左右する大切なものです。
- 「スマホ一つで簡単に…」といった甘い誘い文句に要注意。
- 発信者の信頼性、情報の客観性、手数料の透明性をチェックする。
- 困ったときは、専門家や公的機関など、信頼できる相手に相談する。
お金に関する情報を自分で調べて判断する習慣を身につけることが、何よりも大切です。今日からあなたも、お金に関する「リテラシー」を高めて、怪しい話から自分を守り、賢く豊かな人生を歩んでいきましょう。