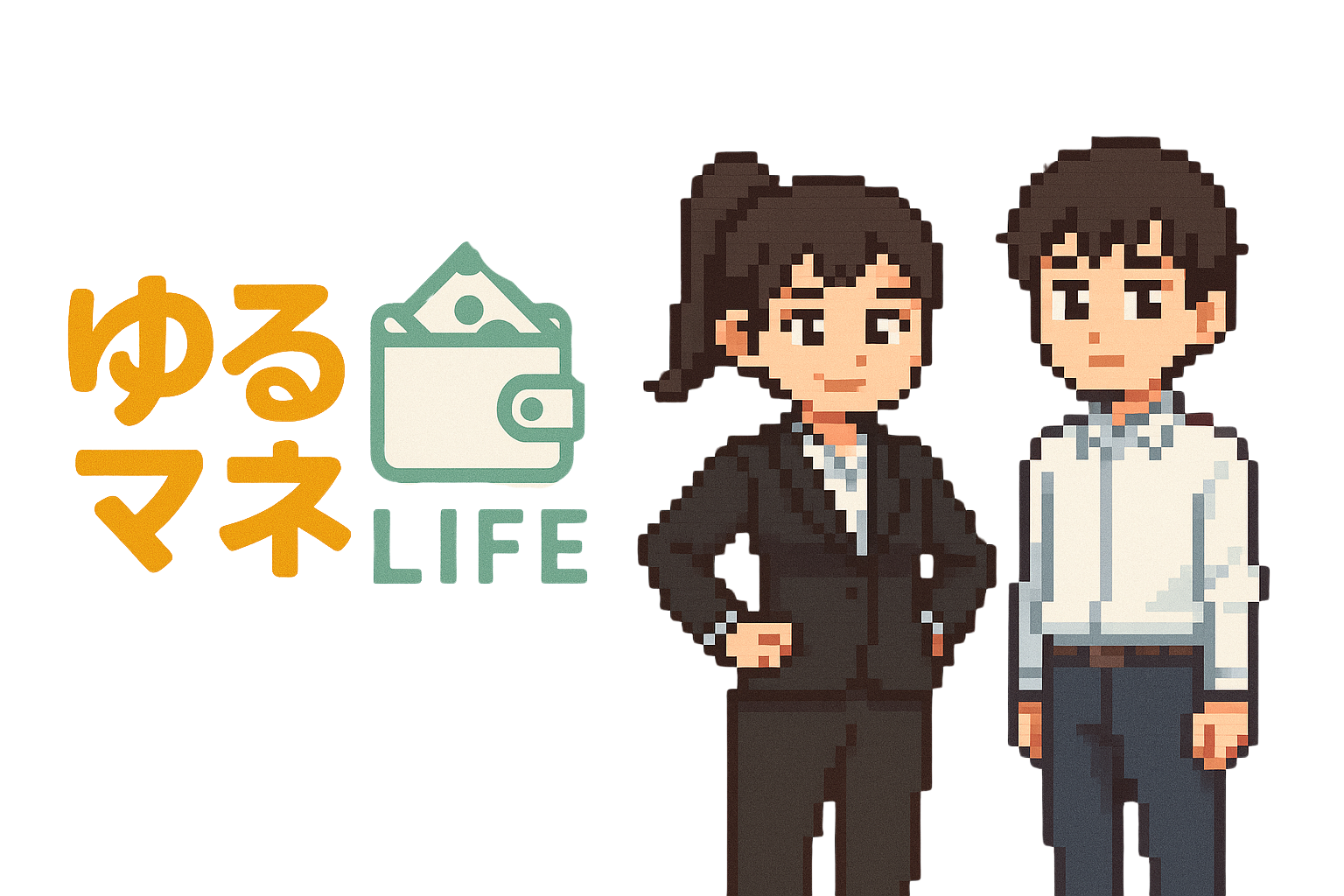【初心者必見】年末調整と確定申告の違いを徹底解説!対象者・控除・手続きの流れまとめ
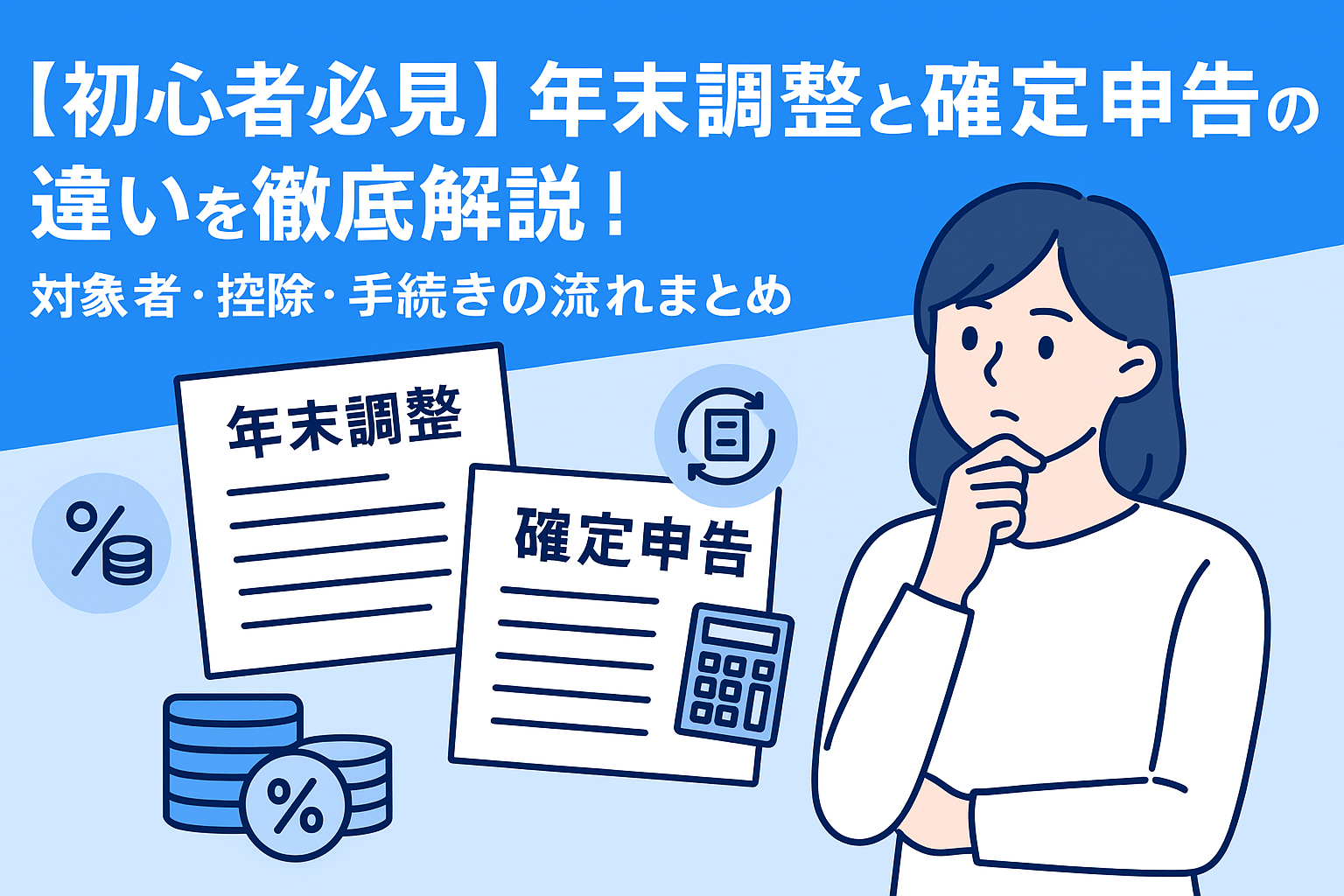
1. 年末調整とは?(復習)
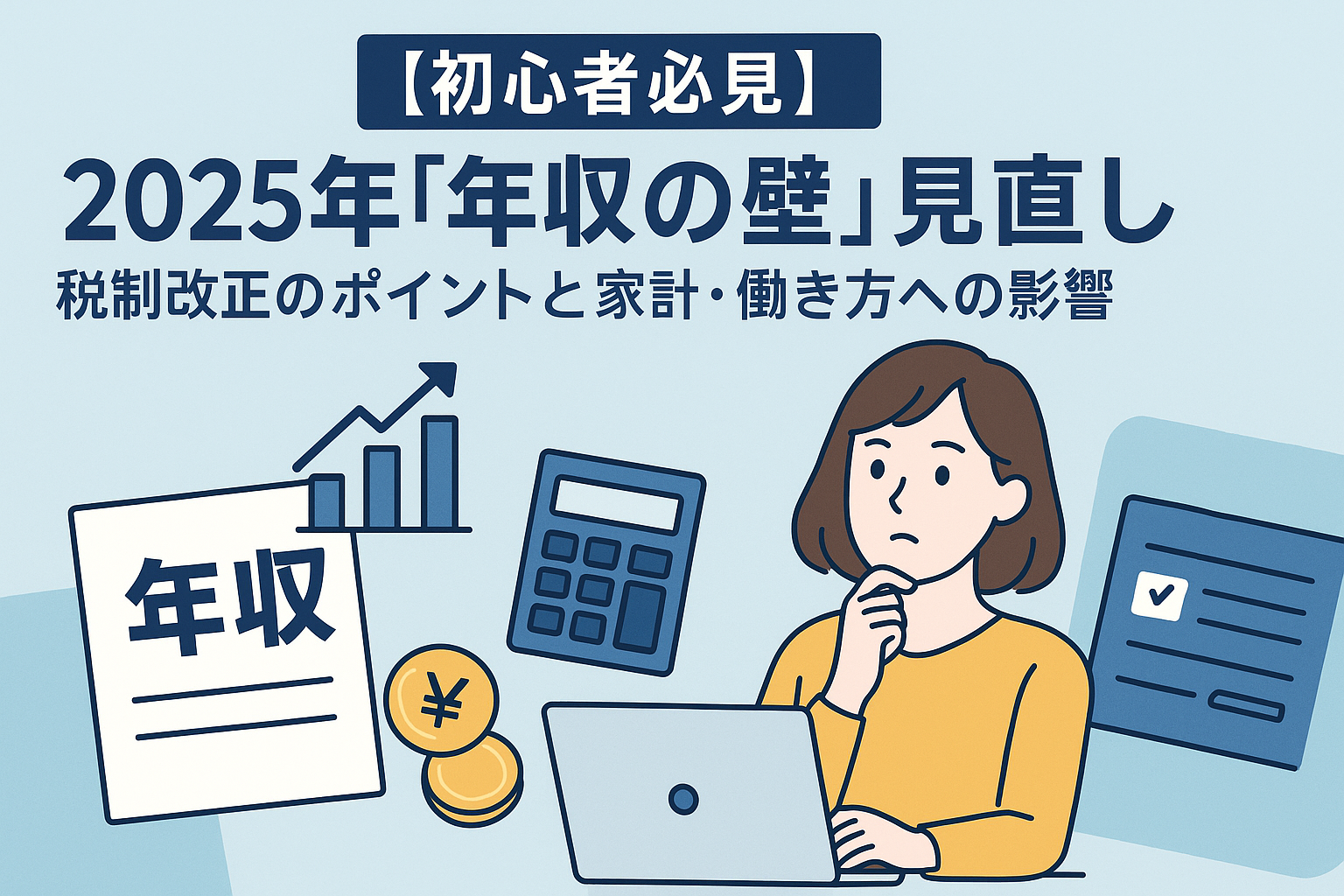
年末調整は、主に会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者が対象となる、1年間の所得税を精算するための手続きです。毎月の給与や賞与から天引きされている所得税(源泉徴収税額)はあくまで概算であるため、その年の給与総額が確定する年末に、正確な税額を計算し、過不足を調整します。
この手続きは、納税者である従業員に代わって勤務先が行うため、従業員自身の手間は比較的少ないのが特徴です。年末調整の結果、源泉徴収額が年間の所得税額よりも多かった場合は差額が還付され、少なかった場合は差額が徴収されます。これにより、従業員は確定申告をする手間なく、正しい納税が完了します。
年末調整の対象者と手続きの時期
年末調整の対象者は、年末調整の基準日(通常は12月末)までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している人です。具体的な対象者は以下の通りです。
- 1年間を通じて勤務している人
- 年の途中で入社し、年末まで勤務している人
- 年の途中で退職した人のうち、特定の条件に該当する人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のため退職し、その年中に再就職が見込めない人
- 12月に給与の支払いを受けた後に退職した人
- パート社員などで退職し、その年中に受け取る給与の総額が103万円以下で、退職後に他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みがない人
- 年の途中で海外支店などへの転勤により非居住者となった人
一方で、以下のような人は年末調整の対象とならず、確定申告が必要になる場合があります。
- 給与の年間収入が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与を受け取っており、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人
- 年末調整に必要な書類(扶養控除等(異動)申告書など)を提出していない人
- いわゆる日雇い労働者や非居住者
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給与に対して、通常は12月に支払われる最後の給与と一緒に行われます。書類の提出は10月末から12月上旬にかけて求められることが一般的です。
年末調整で申告できる控除
年末調整で申告できる主な所得控除は以下の通りです。これらの控除を適用することで、課税所得が減り、最終的な所得税額を抑えることができます。
- 扶養控除: 扶養している親族がいる場合に適用されます。
- 配偶者控除・配偶者特別控除: 所得の少ない配偶者がいる場合に適用されます。
- 社会保険料控除: 健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料などを支払った場合に適用されます。
- 生命保険料控除: 生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合に適用されます。
- 地震保険料控除: 地震保険の保険料を支払った場合に適用されます。
- 小規模企業共済等掛金控除: iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用されます。
これらの控除を受けるためには、勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、生命保険料控除証明書などの必要書類を添付して提出します。
2. 確定申告とは?(復習)
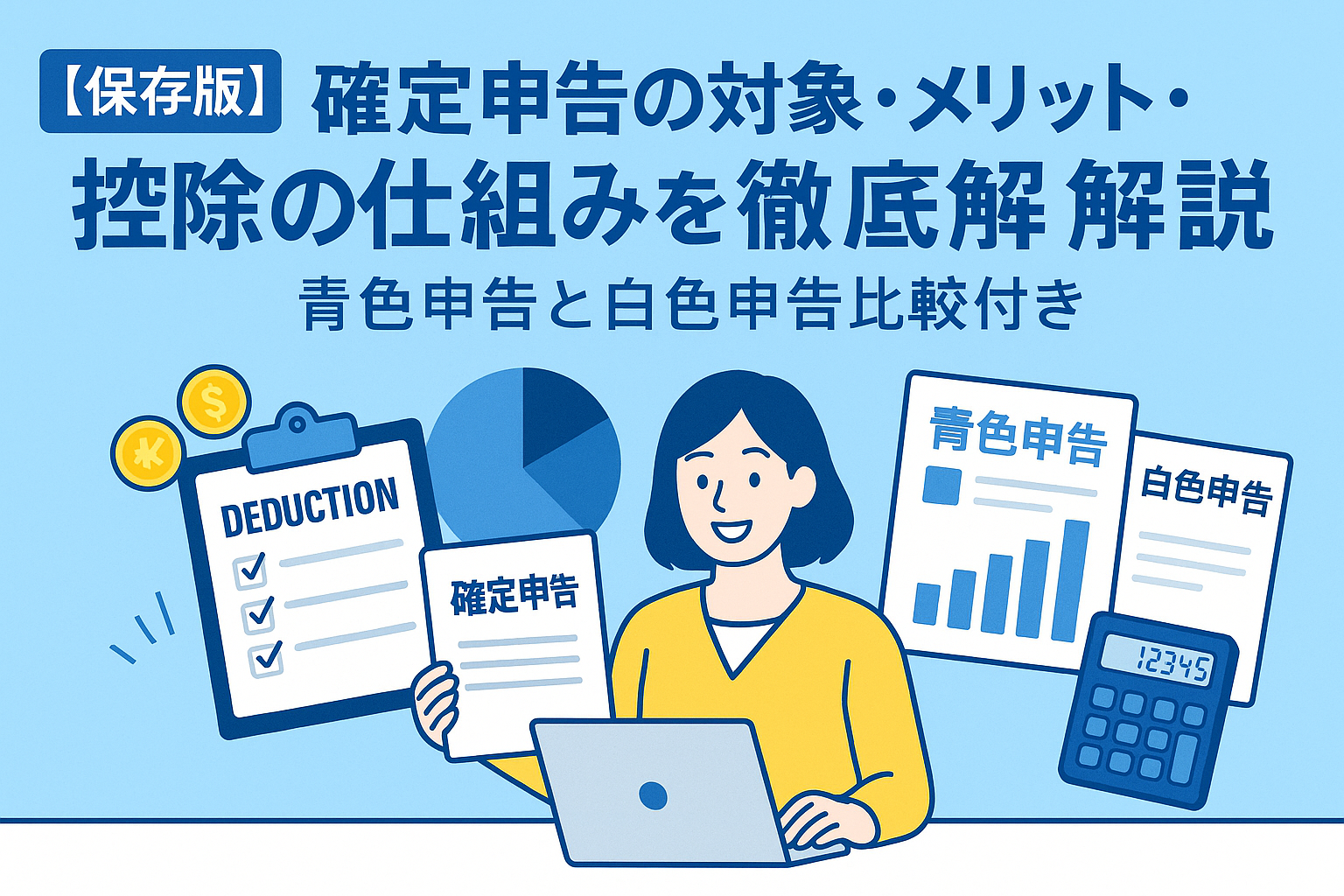
確定申告は、1年間のすべての所得を自分で計算し、税務署に申告・納税する手続きです。年末調整が勤務先主導で行われるのに対し、確定申告は納税者本人が責任を持って行う必要があります。この手続きは、個人事業主やフリーランスだけでなく、特定の条件を満たす給与所得者も対象となります。
確定申告が必要な人・状況
確定申告が必要な主なケースは以下の通りです。
- 事業所得がある人:
- 個人事業主、フリーランス、自営業者など、事業所得がある人は原則として確定申告が必要です。年間所得金額が48万円(基礎控除額)以下であれば所得税は発生しませんが、収入や所得の証明のために申告することが推奨されます。
- 給与所得者で年末調整だけでは不十分な人:
- 給与の年間収入が2,000万円を超える人。
- 副業の所得(給与所得や退職所得以外)が年間20万円を超える人。ここでいう「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
- 2か所以上から給与を受け取っており、年末調整されなかった給与収入と副業所得の合計額が20万円を超える人。
- 年の途中で退職し、再就職しなかった人。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取った人。
- 年末調整の書類提出期限に間に合わなかった人。
- 公的年金受給者:
- 公的年金の年間収入が400万円を超える人。
- 年金収入が400万円以下でも、公的年金以外の所得の合計金額が20万円を超える人。
- その他:
- 家賃収入などの不動産所得、株式の譲渡所得など、給与所得以外の所得がある人。
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人。
確定申告をした方が有利な人(還付申告)
確定申告の義務がなくても、申告することで税金が戻ってくる(還付)場合があります。これを還付申告といい、以下のケースに当てはまる人は、確定申告を検討するとよいでしょう。
- 医療費控除を受けたい人: 自分や生計を同一にする家族のために支払った医療費が、年間10万円または総所得金額の5%(所得200万円未満の場合)を超えた場合、控除の対象となります。
- 雑損控除を受けたい人: 災害、盗難、横領により、自分や扶養家族の資産に損害を受けた場合。
- 寄附金控除(ふるさと納税を含む)を受けたい人: 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄附をした場合。特にふるさと納税では、ワンストップ特例制度を利用できない場合に確定申告が必要です。
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて受ける人: 住宅ローンを利用してマイホームを取得・増改築した場合の最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きできます。
- 副業収入から源泉徴収されている人: 副業所得が20万円以下であっても、納めすぎた税金が還付される可能性が高いため、確定申告を行う方が良いでしょう。
確定申告の時期
確定申告の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの所得です。原則として、翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ申告・納税を行います。ただし、還付申告の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでも申告が可能です。
3. 年末調整と確定申告の決定的な違い
年末調整と確定申告の主な違いを以下の表にまとめました。この違いを理解することが、適切な手続きを行うための第一歩です。
📅 年末調整と確定申告の比較表
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
| 対象者 | 主に給与所得者(会社員、パート、アルバイト) | 個人事業主、フリーランス、自営業者、公的年金受給者、特定の条件を満たす給与所得者など |
| 手続きをする人 | 勤務先(会社) | 納税者本人 |
| 対象となる所得 | 主に給与所得 | 1年間(1月1日~12月31日)のすべての所得 |
| 目的 | 毎月の概算納税額を精算する | 1年間の所得と税額を確定させる |
| 手続きの時期 | 毎年12月頃 | 翌年2月16日~3月15日(還付申告はいつでも可) |
| 申告できる控除 | 扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、限定的 | 所得控除全般(医療費控除、雑損控除、寄附金控除など)、税額控除全般(住宅ローン控除など) |
| メリット | 勤務先が代行するため手間が少ない | さまざまな控除を適用することで節税できる可能性がある |
| デメリット | 適用できる控除が限定的 | 自分で書類を準備し手続きする必要がある |
4. 状況別:どちらの手続きが必要?🤔
自分の状況に合わせて、年末調整と確定申告のどちらが必要か、または両方が必要なのかを確認しましょう。
🧑💼 会社員のケース
| 状況 | 手続き | 理由と補足 |
| 給与所得のみで、年収2,000万円以下 | 年末調整のみ | 勤務先がすべて代行してくれるため、基本的に手続きは不要です。 |
| 副業所得が年間20万円超 | 年末調整 + 確定申告 | 給与は年末調整で精算し、副業所得は自分で確定申告が必要です。副業所得が20万円以下でも、源泉徴収されている場合は確定申告(還付申告)をした方が有利です。 |
| 給与所得のみだが、年の途中で退職し再就職しなかった | 確定申告 | 勤務先が年末調整をしてくれないため、自分で手続きする必要があります。 |
| 給与所得のみで、医療費控除やふるさと納税の控除を受けたい | 年末調整 + 確定申告(還付申告) | 年末調整後に確定申告を行うことで、医療費控除や寄附金控除などが適用され税金が還付される可能性があります。 |
| 2か所以上から給与を受け取っている | 年末調整 + 確定申告 | 主な勤務先で年末調整を行い、年末調整されなかった給与と副業所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要です。 |
🧑💻 個人事業主・フリーランスのケース
| 状況 | 手続き | 理由と補足 |
| 年間所得が48万円超 | 確定申告 | 基礎控除額(48万円)を超える所得がある場合、所得税が発生するため申告が必要です。 |
| 年間所得が48万円以下 | 原則不要だが申告が推奨される | 収入や所得の証明として申告するメリットや、青色申告による優遇措置(最大65万円の特別控除など)を受けるために申告が推奨されます。 |
| 赤字が発生した | 確定申告 | 確定申告(特に青色申告)を行うことで、翌年以降3年間赤字を繰り越して所得と相殺できる場合があります。 |
👵 公的年金受給者のケース
| 状況 | 手続き | 理由と補足 |
| 年金収入のみで、年400万円以下かつ年金以外の所得が20万円以下 | 確定申告不要 | 確定申告が不要な「確定申告不要制度」が適用されます。ただし、医療費控除などを受けたい場合は確定申告が必要です。 |
| 年金収入が年間400万円超、または年金以外の所得が20万円超 | 確定申告 | 確定申告不要制度の対象外となるため、確定申告が必要です。 |
5. 副業がある場合の確定申告 💼
近年、副業を行う人が増加していますが、副業からの所得は、所得区分によって手続きやメリットが異なります。
副業所得の区分
副業の所得は、主に事業所得または雑所得に区分されます。どちらに該当するかは、その活動が継続的・反復的に行われ、社会通念上「事業」といえるかどうかで判断されます。
2022年の所得税基本通達の改正により、帳簿・書類を継続的に作成し保存していれば、本業・副業に関係なく、概ね事業所得として認められるようになりました。
雑所得と事業所得の比較表
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
| 定義 | 他の9種類の所得(給与所得や事業所得など)に該当しない所得 | 農業、漁業、製造業、小売業、サービス業など、継続的かつ独立して営まれる事業から生じる所得 |
| 申告方法 | 白色申告のみ | 白色申告、または青色申告 |
| メリット | 特に税制上の優遇措置はない | 青色申告を行うと、最大65万円の特別控除や損失の繰り越しなどのメリットがある |
| 帳簿付け | 義務ではないが推奨される(売上や経費の集計のため) | 65万円控除を受けるには複式簿記による記帳が必要 |
| 提出書類 | 確定申告書 | 確定申告書、青色申告決算書など |
| 主な例 | アフィリエイト、執筆料、講演料、クラウドソーシングによる単発の仕事など | 継続的なウェブ制作、コンサルティング、継続的な物品販売など |
青色申告のメリットと要件
副業が事業所得に該当する場合、事前に手続きを行うことで青色申告を選択できます。青色申告には、白色申告にはない多くの税制上の優遇措置があります。
青色申告の主なメリット:
- 青色申告特別控除: 複式簿記による記帳などの要件を満たし、e-Taxで申告または優良な電子帳簿保存を行えば、最大65万円の控除が受けられます。それ以外の場合でも10万円の控除を受けられます。
- 青色事業専従者給与: 事業を手伝う家族への給与を、一定の要件下で必要経費に計上できます。
- 純損失の繰り越しと繰り戻し: 事業で生じた赤字(純損失)を翌年以降3年間繰り越して所得と相殺したり、前年が黒字だった場合はその赤字を前年分の所得と相殺して還付を受けたりできます。
青色申告の要件:
- 事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。原則として、その年の確定申告期限(3月15日)までに行う必要があります。
- 最大65万円の控除を受けるためには、複式簿記による帳簿の作成や、貸借対照表・損益計算書の添付が必要です。
副業の住民税対策
会社に副業を知られたくない場合、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることで、会社に通知が行くことを防ぐことができます。確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄の「自分で納付」にチェックを入れることで、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で納付することになります。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告が必要な人が申告を怠ったり、期限を過ぎて申告したりした場合、以下のようなペナルティが科される可能性があります。
- 無申告加算税: 納税すべき税額に対して、税務署の調査の通知前であれば5%、通知後であれば10%〜25%が加算されます。
- 延滞税: 法定納期限の翌日から申告書を提出する日までの日数に応じた利息分が加算されます。
- 青色申告特別控除の減額: 青色申告をしていても、期限を過ぎてからの申告では青色申告特別控除が10万円しか適用されません。
6. 具体的な手続きの流れと準備物
年末調整と確定申告では、それぞれ準備する書類や手続きの流れが異なります。
年末調整の手続きの流れと準備物
1. 勤務先から書類を受け取る: 10月〜11月頃、勤務先から以下の書類が配布されます。 *給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 * 給与所得者の保険料控除申告書
2. 必要事項を記入・提出する: 配偶者や扶養親族の情報を記入し、以下の証明書を添付して勤務先に提出します。 * 生命保険料控除証明書 * 地震保険料控除証明書 * 国民年金保険料控除証明書(自分で支払っている場合) * 国民健康保険料の領収書(自分で支払っている場合) * 住宅ローン控除(2年目以降)の証明書
3. 所得税の還付または徴収を受ける: 12月または翌年1月の給与と一緒に、税金の過不足が精算されます。
確定申告の手続きの流れと準備物
1. 1年間の所得と経費を整理する: 1月1日から12月31日までのすべての収入と、それに伴う経費をまとめます。 * 必要経費の領収書やレシート、請求書などを整理しましょう。 * 副業がある場合は、本業の源泉徴収票を勤務先からもらいます。
2. 申告書を作成する: * 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の案内に従ってスムーズに作成できます。 * e-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで申告が可能です。 * 手書きで作成する場合は、税務署や市区町村役場で申告書を入手します。
3. 必要書類を準備する: * 源泉徴収票(給与所得者) * 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書 * 医療費控除の明細書 * 国民年金保険料等の控除証明書 * ふるさと納税などの寄附金受領証明書 * 住宅ローン控除の証明書 * 個人事業主の場合は収支内訳書(白色申告)または青色申告決算書(青色申告)
4. 申告書を提出・納税する: * e-Taxでオンライン提出 * 税務署に持参 * 郵送で提出
納税がある場合は、振替納税やクレジットカード払い、コンビニ払いなどで納税します。還付の場合は、指定の口座に税金が振り込まれます。
7. よくあるQ&A
Q1:年末調整と確定申告、どちらも行った場合、二重に税金を払うことになりますか?
A1: いいえ、二重に税金を払うことにはなりません。確定申告の際には、年末調整で既に精算された所得税額を差し引いて、最終的な納税額が再計算されます。そのため、すでに源泉徴収された額や年末調整で精算された額が差し引かれるので安心してください。
Q2:副業所得が20万円以下なら、確定申告はしなくてもいいですか?
A2: 所得税の申告義務はありません。ただし、副業の収入から源泉徴収されている場合は、確定申告(還付申告)をすることで、源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があります。また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要な場合があります。確定申告を行えば、住民税の申告は別途不要となります。
Q3:確定申告をしないとどうなりますか?
A3: 確定申告の義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科されます。また、青色申告特別控除が受けられないなど、税制上の優遇措置も失われます。
まとめ
年末調整と確定申告は、日本の所得税制度を理解する上で欠かせない手続きです。
- 年末調整:主に給与所得者を対象とし、勤務先が代行する手続き。手続きは簡単だが、適用できる控除は限定的。
- 確定申告:個人事業主やフリーランスが必須で行う手続き。給与所得者も、副業や特定の控除を受けたい場合に必要となる。手間はかかるが、節税の幅が広い。
ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを行うことが大切です。不明な点があれば、税理士や税務署、国税庁のウェブサイトなどを活用して、正しい情報を得るようにしましょう。
この記事が、あなたの年末調整や確定申告に関する疑問を解消する一助となれば幸いです。