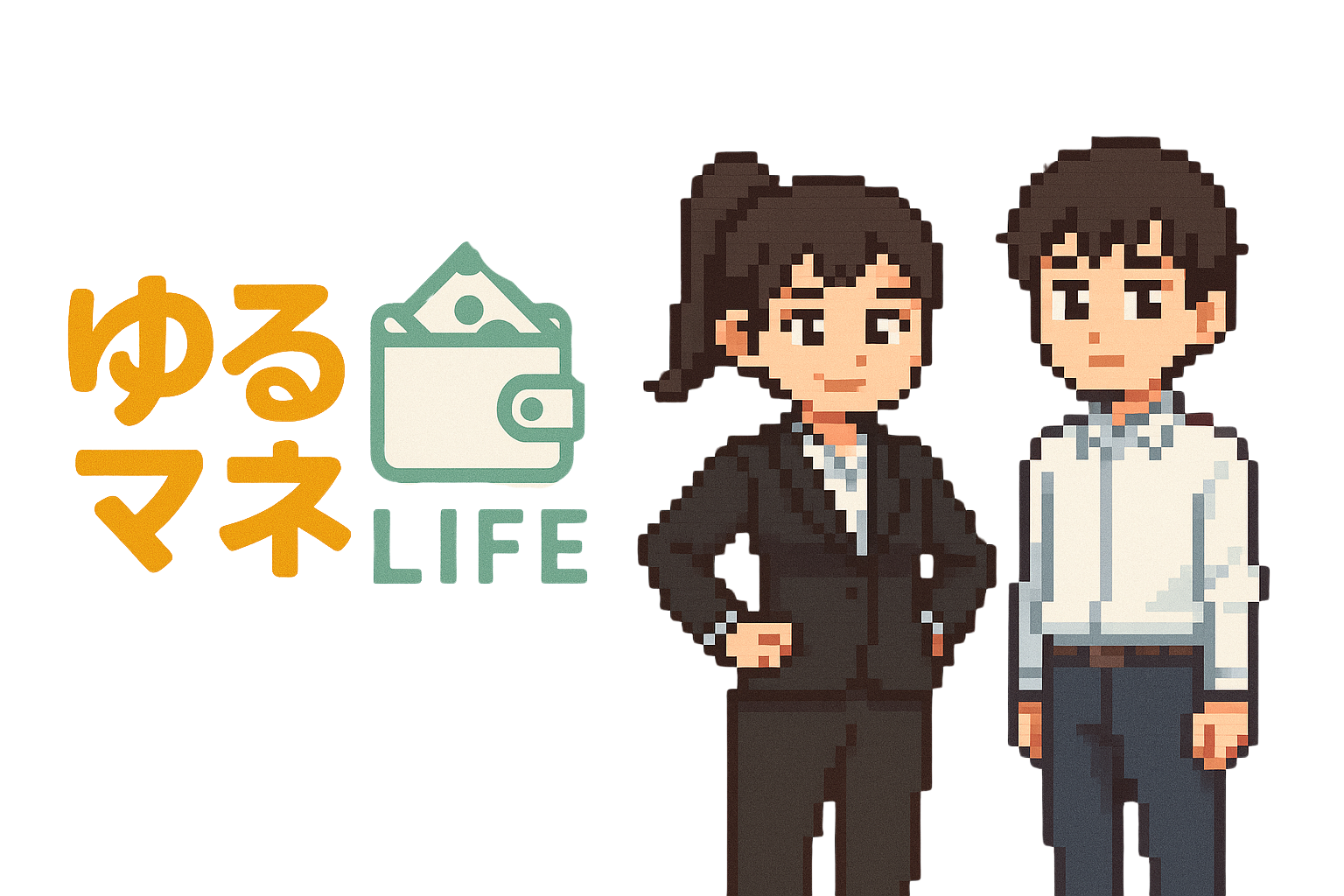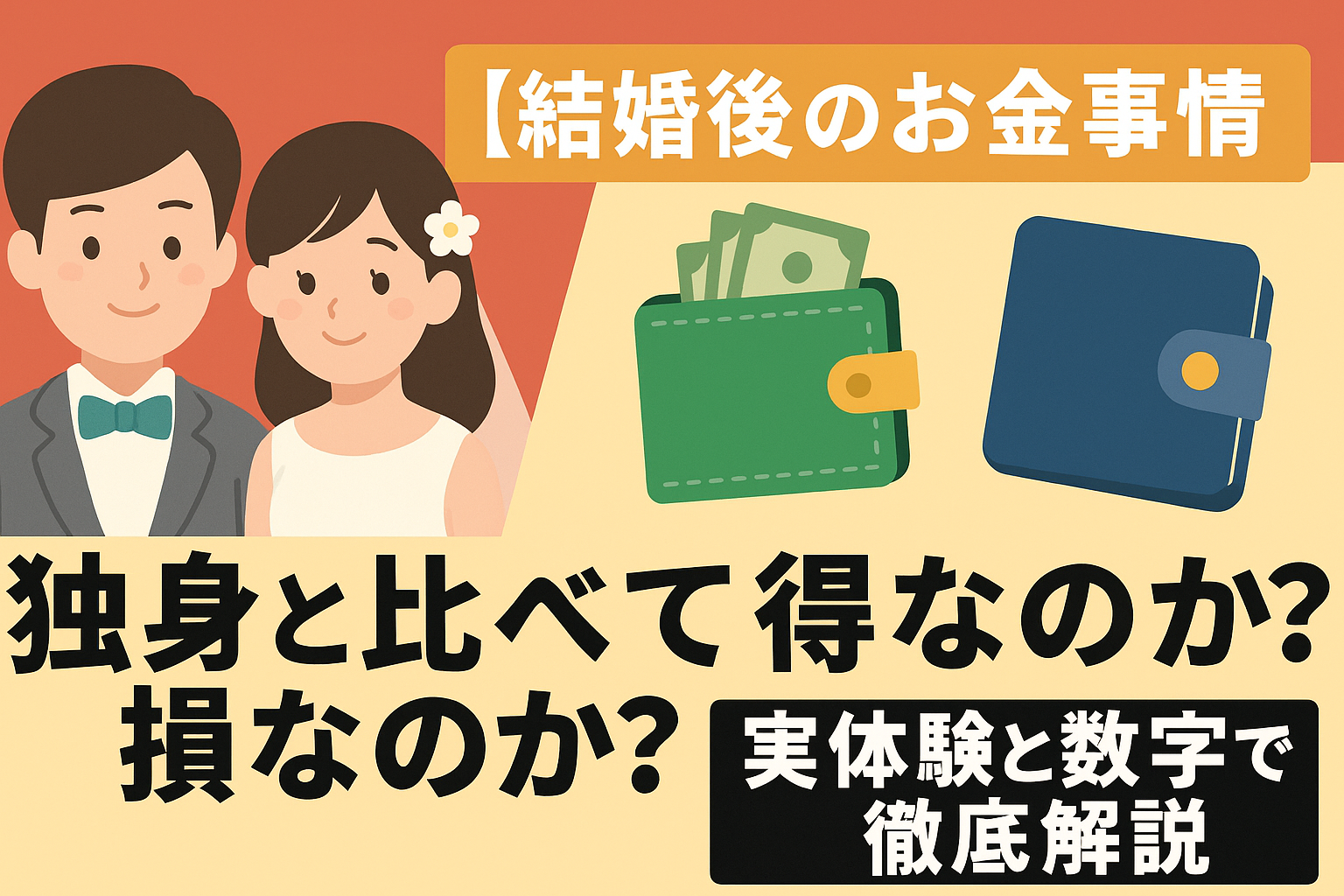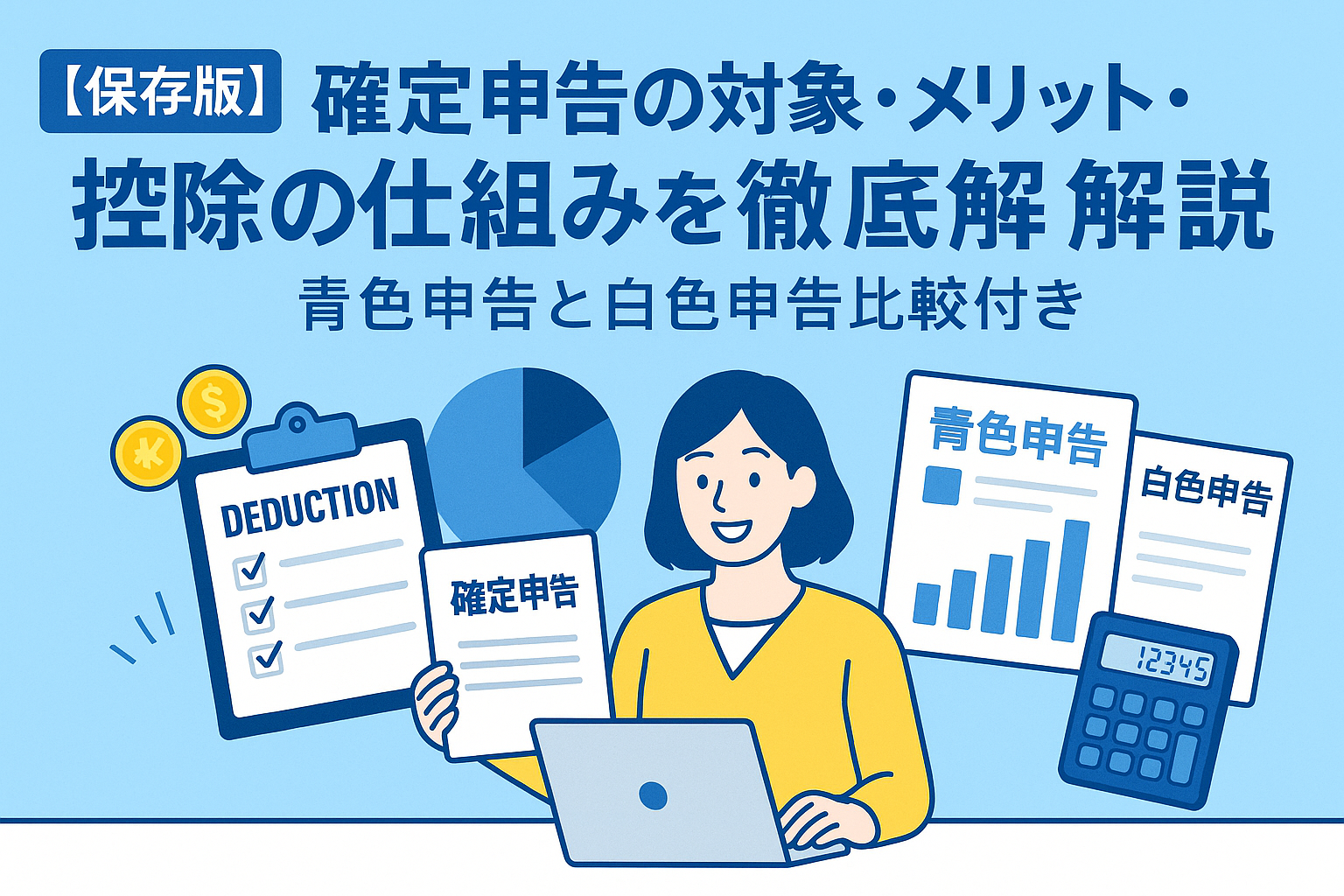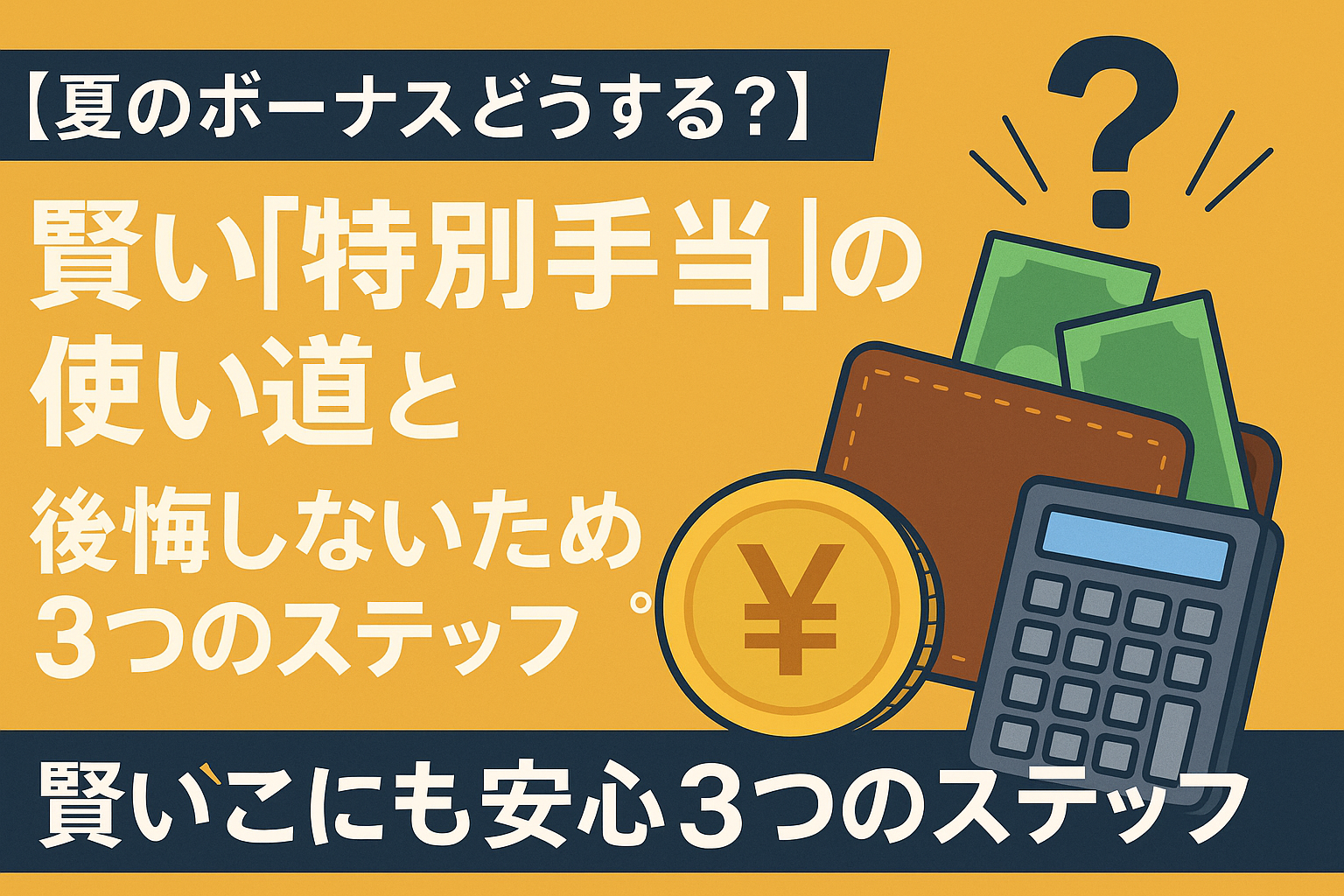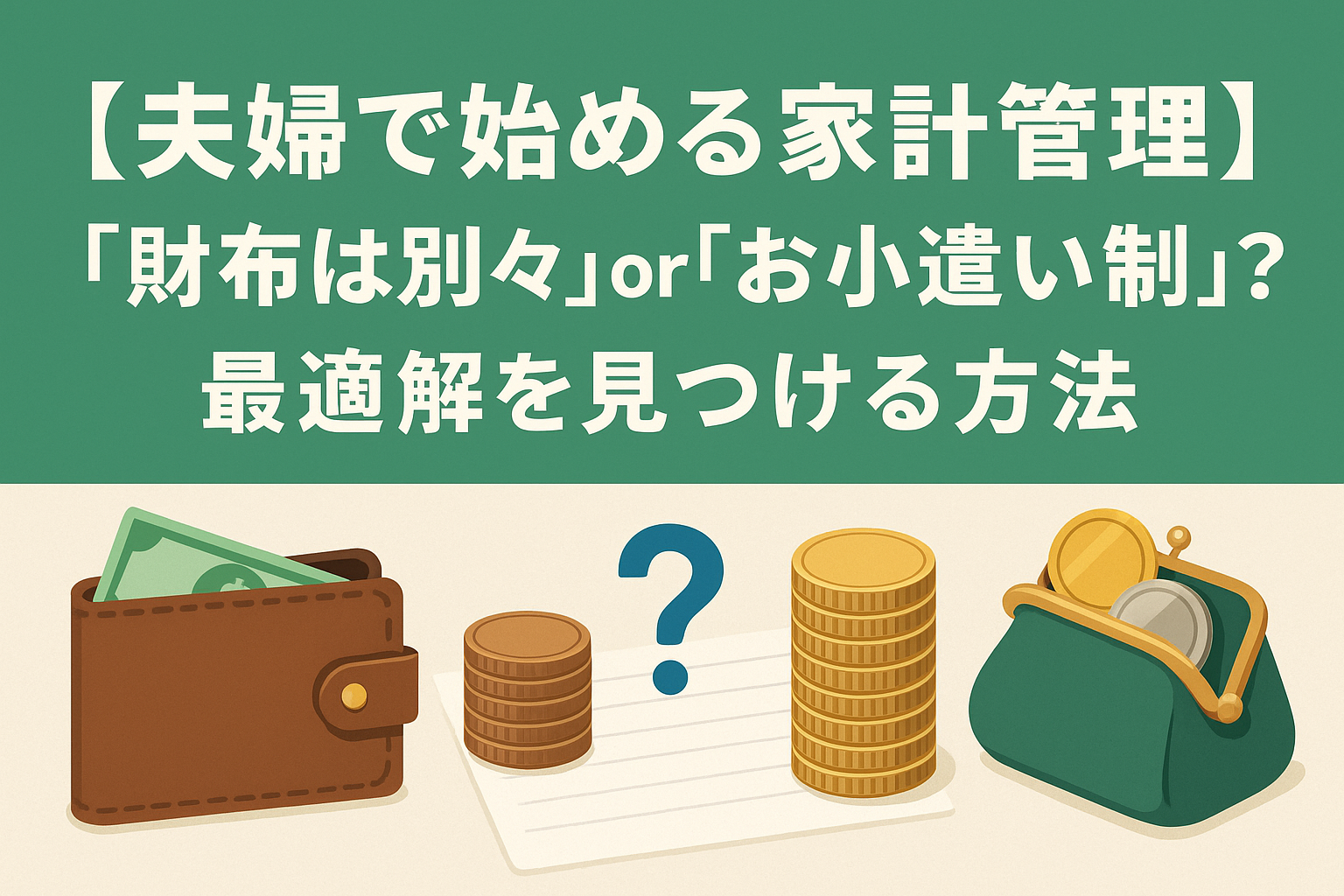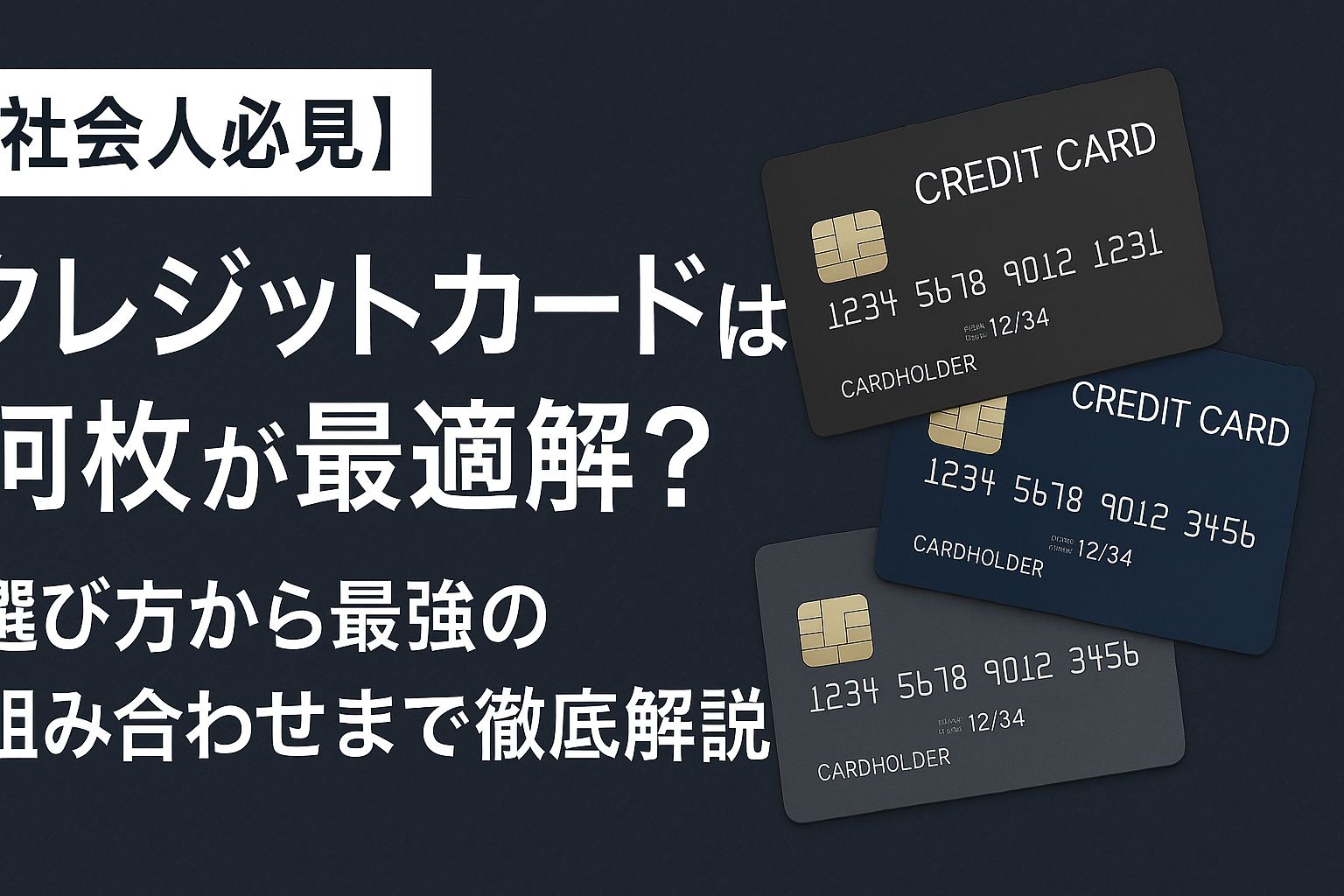【人生100年時代】「親の介護」と「自分たちの老後資金」どう両立する?具体的な備え方


うちのおばあちゃんが今体調悪いんだけど、お母さんが色んなことに不安を感じているみたいなの。

まぁ、なかなか相談しにくいお金の話も含まれるでしょうからね。こういった悩みはため込みがちになりますね。

そうなの、だから私もお母さんの介護と自分の老後のことを少し考えようと思うの!
「もしも」の時、どうする?親の介護と自分たちの老後資金、この不安を解消しよう
「人生100年時代」と言われる今、長生きは喜ばしいことである反面、老後資金や健康寿命への不安を感じる人も多いでしょう。特に、「親の介護」と「自分自身の老後資金」をどう両立していけばいいのか、漠然とした不安を抱えている方は少なくありません。
- 「介護費用って、結局いくらかかるの?」
- 「介護で仕事を辞めることになったら、自分たちの老後資金が…」
- 「親とは介護の話、しにくいんだけど…」
このような悩みを抱えているあなたは、決して一人ではありません。
この記事では、介護にかかる費用や公的制度の知識を分かりやすく解説し、あなたの老後資金を守りながら、親の介護に賢く備えるための具体的なステップを徹底的にご紹介します。切実な問題だからこそ、早めに正しい知識を身につけ、備えを始めることが大切です。
この不安を解消し、親子ともに安心して過ごせる未来を一緒に築いていきましょう。
なぜ「親の介護」と「自分の老後」の両立が難しいのか?
親の介護と子世代の老後資金準備。この二つの問題が複雑に絡み合い、両立が難しくなっている背景には、いくつかの共通の課題があります。
- 介護費用の高騰と長期化:
- 生命保険文化センターの調査(2021年)によると、介護にかかる費用は、一時費用が平均約74万円、月々にかかる費用が平均約8.3万円とされています。
- 介護期間は平均約5年1ヶ月ですが、中には10年以上にわたる長期の介護が必要となるケースも少なくありません。
- この費用は、介護サービス費だけでなく、食費、おむつ代、交通費、リフォーム費用、家賃なども含まれます。
- 「介護離職」による収入減のリスク:
- 厚生労働省のデータによると、年間10万人近い人々が「介護」を理由に離職していると言われています。
- 介護のために仕事を辞めたり、勤務時間を短縮したりすることで、子世代の収入が途絶えたり減ったりし、自分たちの老後資金準備が滞るリスクが生じます。
- 子世代の老後資金準備期間の短縮:
- 親の介護が始まる時期は、子世代が自身の老後資金を本格的に準備する、ちょうど働き盛りの時期と重なることが多くあります。
- 介護費用を負担することで、NISAやiDeCoなどでの積立が中断・減額され、自分たちの老後資金が不足する可能性が出てきます。
「介護の現実」を知る:公的介護保険制度と利用できるサービス
漠然とした不安を解消するためには、まず日本の公的介護保険制度について正しく理解することが第一歩です。
1. 介護保険制度の基本
- 加入義務と保険料: 40歳以上になると、介護保険料の支払いが義務付けられます。保険料は年齢や所得、加入している医療保険によって異なります。
- 要介護認定の仕組み: 介護保険サービスを利用するには、自治体への申請が必要です。心身の状態に応じて「要支援1・2」または「要介護1~5」の認定を受けます。
2. 利用できるサービス
要介護認定を受けると、その状態に応じて様々なサービスを1割~3割の自己負担で利用できます。
- 居宅サービス: 自宅で生活しながら利用するサービスです。
- 訪問介護: ホームヘルパーが自宅に来て、入浴・食事の介助や家事援助などを行います。
- 訪問看護: 看護師が自宅に来て、医療的なケアを行います。
- デイサービス(通所介護): 日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどを利用します。
- ショートステイ(短期入所生活介護): 短期間施設に入所し、介護サービスを受けます(家族の休息や出張時など)。
- 施設サービス: 施設に入所して生活するサービスです。
- 特別養護老人ホーム: 要介護3以上が原則。費用が比較的安価ですが、入所待ちが長い傾向があります。
- 介護老人保健施設: 病状が安定し、リハビリ中心のケアが必要な方向け。
- 介護医療院: 長期的な医療と介護が必要な方向け。
3. 自己負担額と上限
- 介護保険サービスの自己負担割合は、所得に応じて1割、2割、または3割です。
- 「高額介護サービス費制度」: 1ヶ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。これにより、自己負担が過度に膨らむのを防ぎます。
介護費用、結局いくら必要?具体的なシミュレーション
介護保険サービスがあるとはいえ、すべてをカバーしてくれるわけではありません。介護の形によって必要な費用は大きく異なります。
在宅介護の場合
- 月々の自己負担額: 介護サービスの自己負担分に加え、食費、水道光熱費、おむつ代、訪問介護でカバーできない生活援助(通院介助のタクシー代など)、住宅改修費などがかかります。
- 平均費用: 月々約5万円~10万円が目安と言われることが多いですが、介護度や利用サービスによって大きく変動します。
施設介護の場合
- 入居一時金(初期費用): 数十万円~数百万円、高額な施設では数千万円かかることもあります。
- 月々の費用: 介護サービス費の自己負担分に加え、食費、居住費、日常生活費などがかかります。
- 平均費用: 特別養護老人ホーム(公的施設)なら月々約8万~15万円程度。有料老人ホーム(民間施設)は月々約15万円~30万円以上と幅広く、施設のグレードやサービス内容によって大きく異なります。
【重要】介護保険サービスではカバーできない費用を明確に! 上記のシミュレーションはあくまで目安です。実際には、以下のような費用も発生します。
- 差額ベッド代(個室など)
- 交通費(通院、家族の面会など)
- 日用品(衣類、消耗品など)
- お小遣い、趣味・娯楽費
- リフォーム費用(手すりの設置、段差解消など)
これらの「介護保険外の費用」も考慮に入れた上で、具体的な備えを考える必要があります。
「自分たちの老後資金」を守りながら親の介護に備える具体的なステップ
介護はいつ始まるか分かりません。だからこそ、早めに計画を立て、冷静に準備を進めることが重要です。
ステップ1:親の資産・年金状況を把握する
まずは、親がどれだけの資産や収入を持っているかを確認しましょう。
- 預貯金、不動産、有価証券: どれくらいの金融資産があるのか、自宅は持ち家かなどを確認します。
- 年金収入: 公的年金(国民年金・厚生年金)の受給額や、個人年金保険などの有無と受給額を把握します。
- なぜ確認するのか?: 親の資産で介護費用をどこまでまかなえるかを知ることが、子世代が負担すべき金額を明確にする第一歩だからです。親のプライバシーに配慮しつつ、理解と協力を得ながら進めましょう。
ステップ2:親と「介護について」具体的に話し合う
これが最も重要で、かつ難しいステップかもしれません。しかし、早めに話し合うことで、将来の選択肢が広がります。
- 介護が必要になった際の希望: 「在宅介護を希望するのか」「施設に入所したいのか」「どこで生活したいのか」など、親の希望を尊重し、具体的に話し合いましょう。
- 費用負担について: 親の資産で不足する場合、子世代がどの程度負担できるのか、兄弟姉妹がいる場合はどのように分担するのかなど、具体的に話し合っておくと安心です。
- エンディングノートの活用: 親の意向、資産情報、連絡先、医療に関する希望などを記したエンディングノートを書いてもらうよう提案するのも良い方法です。
ステップ3:不足する介護費用を算出する
親の資産と公的介護保険サービスでまかなえる部分を差し引き、不足する介護費用を予測します。
- 月々の不足額: 親の月々の収入(年金など)と介護保険サービスでの自己負担額、介護保険外費用を考慮し、月々いくら不足するかを算出します。
- 一時的な不足額: 自宅改修費や施設入居一時金など、一時的にかかる費用を予測します。
- この不足額が、子世代が備えるべき具体的な金額の目安となります。
ステップ4:子世代自身の老後資金計画を見直す
介護費用を見積もったら、次にあなた自身の老後資金計画にどう影響するかを確認し、必要に応じて見直しましょう。
- NISAやiDeCoの拠出額: 現在の積立額が、介護費用の負担と両立できるか再確認します。もし介護費用負担が大きくなる見込みであれば、一時的に積立額を調整することも検討します。
- 退職までの資産形成目標: 親の介護と並行して、自分たちの老後資金が目標通りに形成できるかシミュレーションし、必要であれば調整します。
ステップ5:「介護保険(民間)」の必要性を検討する
公的介護保険で不足する部分を補うために、民間の介護保険への加入を検討することも選択肢の一つです。
- 賢い選び方: 給付金が一時金で受け取れるタイプや、月額で年金のように受け取れるタイプなどがあります。公的制度でカバーできない「一時的な出費」や「介護保険外費用」を補う目的で検討しましょう。
- 注意点: 貯蓄でまかなえる範囲であれば、必ずしも民間保険は不要という視点も持ちましょう。保険料は「掛け捨て」になる可能性も考慮し、慎重に判断することが大切です。
精神的・肉体的負担を減らすための情報収集と相談先
介護は経済的な負担だけでなく、精神的・肉体的な負担も非常に大きいです。一人で抱え込まず、早めに専門家や公的機関に相談しましょう。
- 地域包括支援センター: 地域の高齢者の総合相談窓口です。介護保険の申請支援、介護サービスに関する情報提供、保健・医療・福祉の相談に乗ってくれます。
- ケアマネージャー: 要介護認定後に、介護サービスの計画(ケアプラン)を立ててくれる専門家です。
- ポイント: 複数のケアマネージャーと話して、相性の良い人を選ぶことも大切です。
- 介護の専門家(FP、社会福祉士など): 経済面も含めた総合的な相談ができます。
- 介護と仕事の両立支援制度: 会社員の場合、介護休業(家族1人につき通算93日まで)、介護休暇(年5日まで)など、国や企業が設けている制度があります。勤務先の担当部署に確認しましょう。
まとめ:早く知り、早く備え、安心して向き合える未来へ
「親の介護」と「自分たちの老後資金」の両立は、確かに大きな課題ですが、決して乗り越えられないものではありません。
- 親の資産・年金状況を把握し、親と介護について話し合う
- 公的介護保険制度を理解し、不足する費用を具体的に算出する
- 自分たちの老後資金計画と介護費用を両立できるか見直す
- 必要に応じて、民間保険や専門家への相談も検討する
- 一人で抱え込まず、地域や国の支援制度を活用する
これらのステップを踏むことで、漠然とした不安を具体的な「備え」に変え、親も子も安心して向き合える未来を築くことができます。
さあ、今日からあなたも「人生100年時代」を見据えた、賢い介護と老後資金の準備を始めてみませんか?

……お母様とおばあ様の体調は大丈夫ですか?

さあ?

先輩そういうところありますよね。